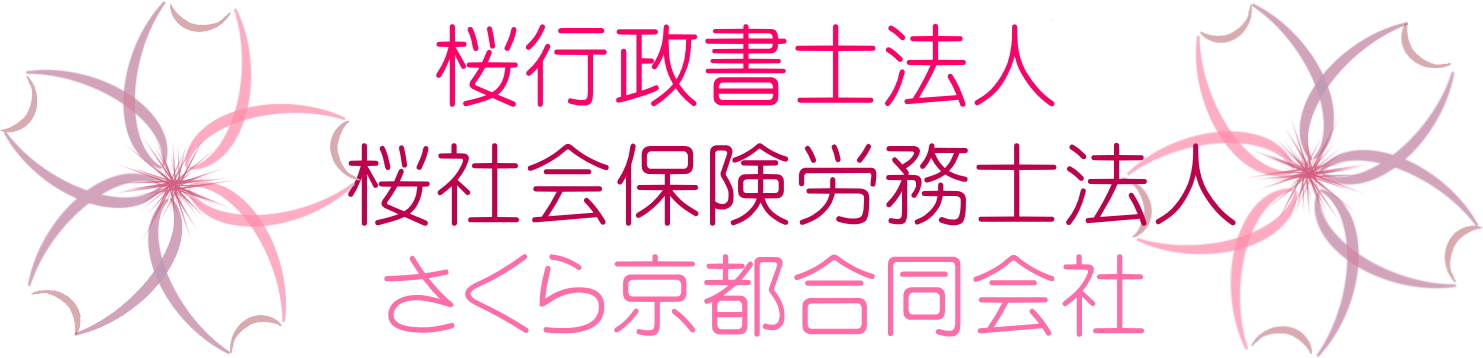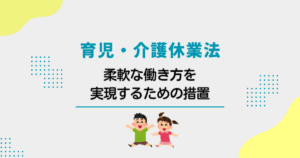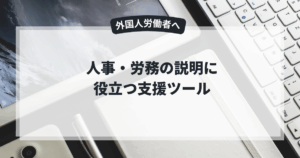預貯金の仮払い制度とは?
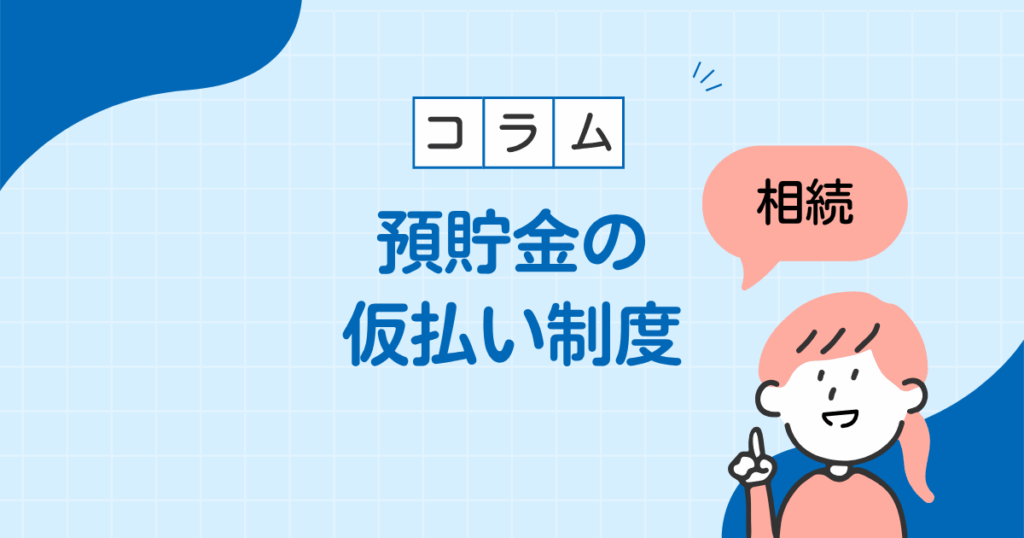
2019年7月の民法改正により、「預貯金の仮払い制度」がつくられました。「預貯金の仮払い制度」について簡単にご紹介します。
預貯金の仮払い制度 概要は
口座名義人が死亡したことを金融機関が把握した場合に、金融機関がその口座からの払い戻しや引き落としを止める「口座凍結」が行われます。本来であれば法定相続人全員で遺産分割協議を行い、手続きを経て預貯金を引き出すことができるようになります。「預貯金の仮払い制度」を利用することにより、遺産分割が終わっていない段階でも一定の金額までなら金融機関から預金を引き出すことができます。しかし、遺言による「遺贈」等があった場合にはこの「預貯金の仮払い制度」は利用できませんので注意が必要です。
「預貯金の仮払い制度」の手続きは直接金融機関に行います。相続人が複数人いる場合でも単独で申請でき、家庭裁判所の許可も不要です。次の①か②のいずれか少ない金額が1つの金融機関から引き出せる上限額となります。
- 故人の死亡時の預金残高 × 1/3 × 申請者の法定相続分
- 150万円(金融機関ごとの上限額)
※1つの金融機関に複数の口座があっても、その金融機関から仮払いを受けることができるのは最大150万円までです。
手続きに必要な書類
- 亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本、または法定相続情報一覧図
- 仮払いを希望する相続人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑証明書
- 金融機関所定の申請書
※金融機関により、必要となる書類が異なる場合がありますのでご利用の際は該当の金融機関にご確認ください。