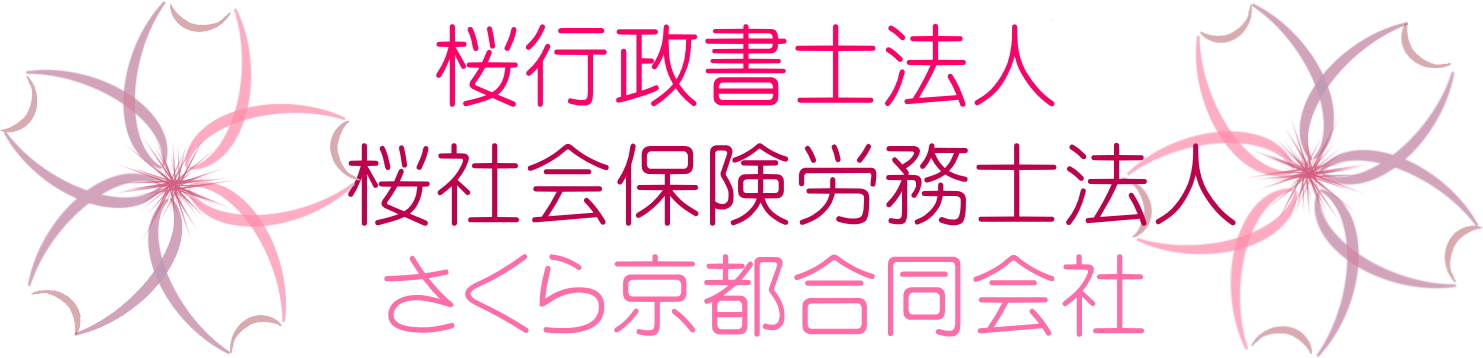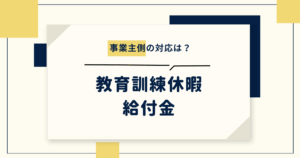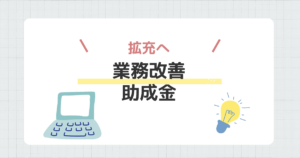「自筆証書遺言書保管制度」相続人側の手続きは?
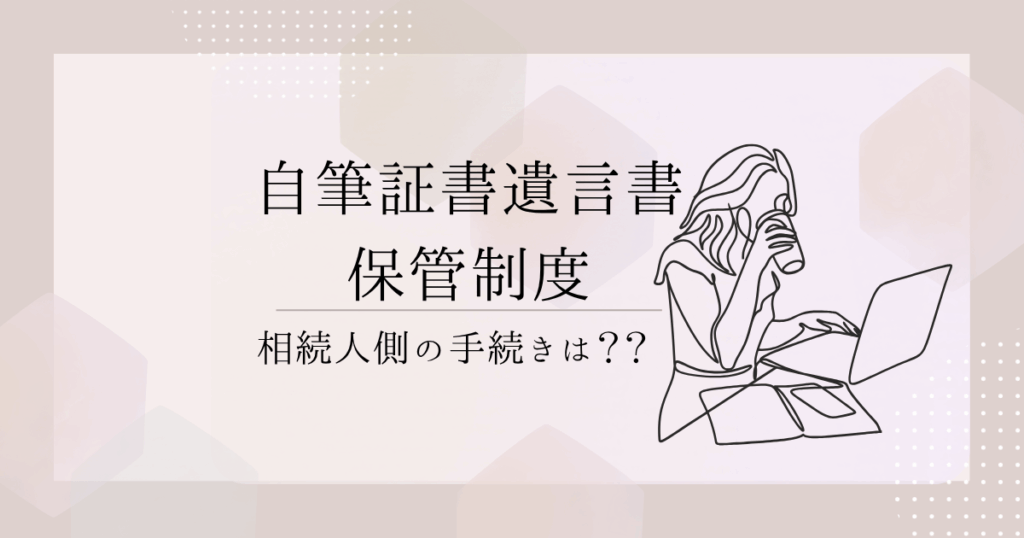
自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」。遺言者の方が亡くなった後(相続開始後)、相続人が行える手続きついてご紹介します。
「自筆証書遺言書保管制度」についてのブログはこちら
遺言書保管事実証明書の交付の請求
「遺言書保管事実証明書」を交付してもらうことで、自分を相続人や受遺者等・遺言執行者等とする遺言書が遺言書保管所(法務局)へ預けられているかどうかを確認することができます。相続人、受遺者等・遺言執行者等の方、その親権者や後見人等の法定代理人が請求することができます。
遺言書情報証明書の交付の請求
「遺言書情報証明書」を交付してもらうことで遺言書の内容を確認することができます。「遺言書情報証明書」には、遺言書の画像情報が全て印刷されています。また、遺言書保管所に保管された遺言書は、遺言者自身からの撤回以外には、相続人であっても返還することはできませんので、遺言書原本の代わりとして相続登記や銀行の手続き等、各種手続に使用いただくこととなります。取得後には家庭裁判所の検認を受ける必要はなくそのまま使用できます。相続人、受遺者等・遺言執行者等の方、その親権者や後見人等の法定代理人が請求することができます。
遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求
相続人等の方は、遺言書の内容を確認するため、遺言書保管所に対して、遺言書の閲覧の請求をすることができます。相続人、受遺者等・遺言執行者等の方、その親権者や後見人等の法定代理人が請求することができます。
いずれの手続きも来庁して交付を受けるには遺言書保管所の予約が必要になります。必要書類等詳細はこちら