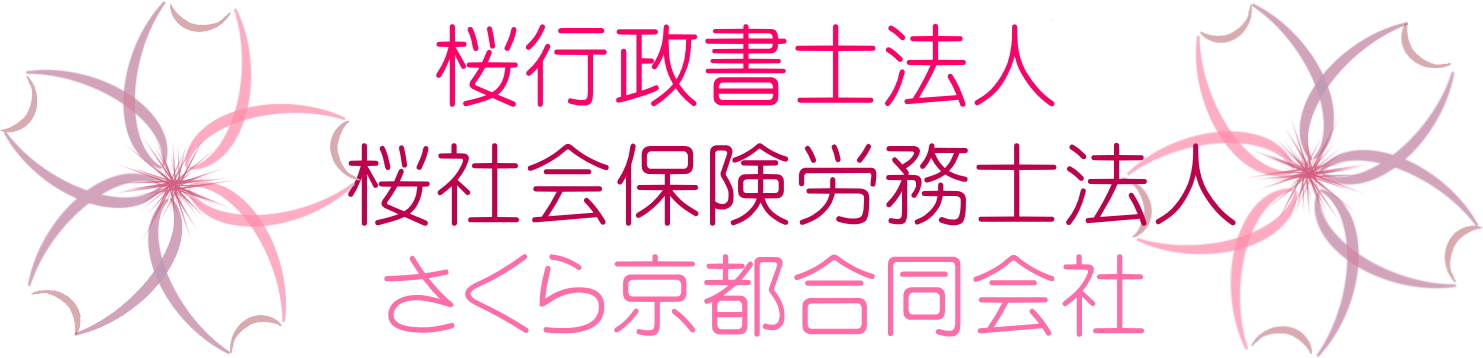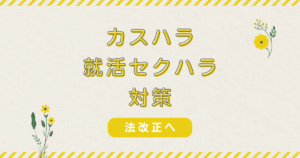成年被後見人・被保佐人・被補助人の違いとは??
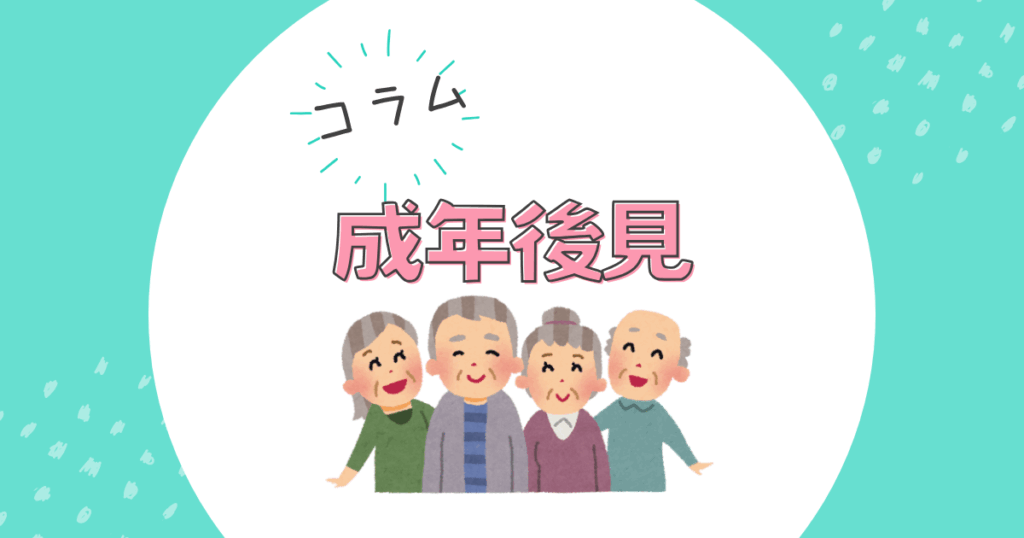
成年後見人制度は、認知症などにより判断能力が不十分である方の法律行為を支援する制度です。成年後見人制度には、成年被後見人・被保佐人・被補助人の3種類がありそれぞれ特徴が異なります。概要や違い、それぞれの対象者が自分でできることなどを簡単に解説します。
成年被後見人、被保佐人、被補助人の概要一覧
| 援助される人 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
| 判断能力の程度 | 判断能力を常に欠く | 判断能力が著しく不十分 | 判断能力が不十分 |
| 対象となる人 | 手続きや契約をひとりでするのが難しい方 | 重要な手続きや契約をひとりでするのが心配な方 | 一部の重要な契約・手続きをひとりでするのが心配な方 |
| 援助する人 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
| 援助する人の同意が必要な行為と援助する人が取り消し可能な行為 | 契約など、全ての法律行為 | 借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築など民法第13条1項所定の行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判により定める特定の法律行為(民法第13条1項所定の行為の一部) |
成年被後見人が自分でできること
法定後見制度のうち、最も手厚いサポートが必要となるため、成年被後見人は単独での法律行為はできません。しかしながら、日用品の購入など日常生活に関する一般的な行為や結婚・離婚・離縁・養子縁組(節税目的などの場合を除く)などの身分行為や、選挙権・被選挙権の行使は成年後見人の同意なしに行うことができます。また、これを成年後見人が取り消すことはできません。
被保佐人が自分でできること
成年被後見人と後述する被補助人の中間的な位置にあたる被保佐人は、一定の法律行為をするのにあたってサポートを必要とする人です。表に挙げた保佐人の同意を必要とする一定の法律行為以外であれば単独でおこなえます。遺言書作成や結婚のほか、日常生活において必要となる軽微な法律行為についても被保佐人は単独でおこなうことが可能です。保佐人は被保佐人がおこなう一定の法律行為について同意権と取消権を行使しますが、被保佐人は保佐人のサポートを受け自ら法律行為をおこなうのが基本であり、原則として保佐人に代理権は付与されません。
被補助人が自分でできること
法定後見制度のうち、最もサポートの範囲が小さいのが被補助人です。被補助人がひとりでできないのは、本人がサポートを希望し裁判所が認めた法律行為に限られます。ほとんどの法律行為をひとりでおこなえますが、本人がサポートを希望し裁判所が認めた法律行為に関しては補助人により同意権・取消権・代理権が行使されます。
コラムNo.57